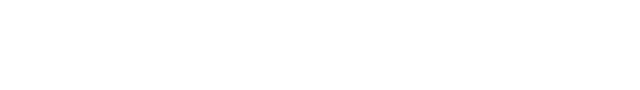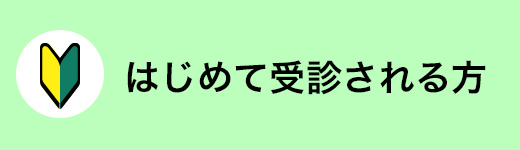小児科の診療案内
小児の疾患は年齢に応じて起こしやすい疾患があり、守備範囲も広いのが特徴です。
中でも身近な疾患の多くは、急性の発熱性疾患です。
迅速診断検査や血液検査、レントゲン検査などを用いることにより、発熱の原因をできる限り明らかにすることを心掛け、不必要な抗生剤の投与などを避けたいと考えております。
感染症の他にも、発疹、便秘、頭痛、腹痛など様々な症状に対応させていただきます。
また、当院では病気の診療や予防接種検診だけではなく、子育てに不安や悩みを抱えるご家族に手を差し伸べ、サポートを行う場所でありたいと考えています。
みなさまの「かかりつけ小児科医」としてお子さまの病気を幅広く診察し、お子様の健康と成長をご家族の皆様と一緒に支援してまいります。
一般外来
「お子さまの感染予防に配慮した安全な待合室・診察室となるよう職員一同に心がけています」
一般診察は2階のフロアで行っています。感染症のお子さまの待合室・診察室と非感染症のお子さまの待合室・診察室を別々に用意しています。また、感染症のお子さまの待合室のために個室(3室)を用意しています。感染症のお子さまの診察後には、診察室と個室の消毒等を行い感染防止対策に努めています。
乳幼児健診・予防接種は「クリーンエリアの3階フロア」で行っています。
(前日20時より受付 15分単位で予約)
診察場所
-
一般診察は2階のフロアで行っています。感染症のお子さまの待合室・診察室と非感染症のお子さまの待合室・診察室を別々に用意しています。また、感染症のお子さまの待合室のために個室(3室)を用意しています。感染症のお子さまの診察後には、診察室と個室の消毒等を行い感染防止対策に努めています。
乳幼児健診・予防接種は「クリーンエリアの3階フロア」で行っています。 - 感染症(感冒症状、胃腸炎、水痘、おたふくかぜなど)のある方は、建物正面の入口より2階小児科フロアにお越しください。
- 皮膚疾患、アレルギー疾患など感染症以外の受診の方は、建物左のエレベーターあるいは階段を利用し、2階小児科フロアにお越しください。
一般外来の診療時間
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前(8:45~12:00) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ◎ |
| 午後(14:00~18:00) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
※木曜日は令和7年8月より休診となります。
○月、火、水、金曜日の予約受付、電話受付終了時刻は17:30となります。
◎診療時間は8:45~13:00です。
- 麻疹、水痘などの発疹のある病気、インフルエンザ、おたふくかぜの疑いがある方は、受付にお声がけください。
隔離待合室をご案内させていただきます。 - 緊急の場合も受付に直接ご連絡ください。
- 診察は予約をされた方を優先いたします。
予約なしで来院された方は、当日の混雑状況でお待ちいただく場合があります。 - 時間外の診察は川崎市救急情報センター(044-222-1919)にお問い合わせください。
乳幼児健診・予防接種
「お子さまの感染予防に配慮した安全な待合室・診察室となるよう職員一同に心がけています」
一般診察は2階のフロアで行っています。感染症のお子さまの待合室・診察室と非感染症のお子さまの待合室・診察室を別々に用意しています。また、感染症のお子さまの待合室のために個室(3室)を用意しています。感染症のお子さまの診察後には、診察室と個室の消毒等を行い感染防止対策に努めています。
乳幼児健診・予防接種は「クリーンエリアの3階フロア」で行っています。
診察場所
3階フロアで行います。
来院時は建物正面右側の入り口から入りエレベーターをご利用ください。
基本的には3階フロアで受付を行いますが、時間帯によっては2階小児科フロアで受付を行うこともあります。
(お風邪の方と待合は別にさせていただきます)
乳幼児健診・予防接種の診療時間
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前(8:45~11:45) | △ | △ | ○ | - | ○ | ○ |
| 午後(14:00~17:00) | △ | △ | ○ | - | ○ | - |
▲、△の予約枠はわずかです。
※乳幼児健診と予防接種を同時に予約できます。
ご希望の方は「乳幼児健診と予防接種」で予約し、予約が取れない場合は受付044-865-5247に申し出てください。
乳幼児健診
お子さまの身体発育だけでなく、心の発達の視点からも診察・支援ができるように心がけています。お子さまの気質・性格は十人十色です。個性に合った養育が重要であるからです。
- 乳幼児健診は予約制になります。
受付でも予約を行っておりますので予約が取れない場合はお申し出ください。 - 3~4か月健診は「こんにちは赤ちゃん外来」で受けることをお勧めします。
- 市の補助による健診 3~4か月、7か月、5歳児健診は無料です。
10か月健診は7か月健診のフォロー健診で無料ですが、7か月で必要かどうか判断して実施します。
- 5歳健診にて 当院ではスポットビジョンスクリーナー(ウェルチアレン社)を用いて視覚のスクリーニング検査を行っております。
数秒間注視するだけで弱視(近視、遠視、乱視、不同視など)を発見することが出来る機械です。
検査で異常が疑われた場合は、眼科医療機関を紹介させていただきます。
5歳健診以外でも、お子様の視力に心配がある方はご相談ください。
生後6か月から検査を行うことが出来ます。 - 保育園の入園前健診も行っております。
- 通常の時間帯にご来院の難しい保育園へ通っているお子様や、小学校高学年の方は受付にご連絡ください。
※来院時には下記のものを必ずお持ちください。
- 診察券
- マイナンバーカードあるいは資格確認書と医療証
- 母子手帳
- 市から配布された問診票
- 体温計
- 来院直前の尿(5歳健診の方、空き容器に5ml程度)
予防接種
ワクチンで予防できる病気VPDに罹らないように、適切な時期に予防接種を受けましょう。お子さまの年齢や成育歴、病歴等を考慮して、お子さまに合ったワクチンスケジュールを提案します。
公費の予防接種は『川崎市から配布されている問診票』に、自費(任意)の予防接種は『当院で用意した問診票』に記入していただいています。
事前に自費用問診票に記入していただける方は、以下のPDFを印刷してください。
異なる種類のワクチンの接種間隔について
注射の生ワクチンどうしを接種する場合は27日以上開ける制限は維持しつつ、その他のワクチンの組み合わせについては、一律の日数制限は設けないことになっています。ただし、同じ種類のワクチンを複数回接種する場合は、ワクチンごとに決め有れている接種間隔に変更はありません。
接種できるワクチンの種類と接種間隔
※ワクチンの同時接種の予約は希望するすべてのワクチンを選択してください。
5種類まで予約することができます。
ワクチンの種類について
注射生ワクチン
麻しん風しん混合ワクチン・水痘ワクチン・BCGワクチン・おたふくかぜワクチン など
経口生ワクチン
ロタウイルスワクチン など
不活化ワクチン
ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン・B型肝炎ワクチン・5種混合ワクチン・日本脳炎ワクチン・季節性インフルエンザワクチン など
- 予防接種に関して詳しくお知りになりたい方は下記のリンクをクリックしてください。
- 予約受付時間においでになれない方は、「一般外来」で予約を取り、来院時に「予防接種」である旨を申し出てください。
- 当日は母子手帳と予診票をあらかじめご記入の上、ご持参ください。
なお、任意接種の場合は、自費用問診票に記入していただきます。 - インフルエンザの予約は、9月頃より電話・ホームページで案内します。
予約は受診の際に受付でも行っております。
コロナワクチン予防接種について
コロナワクチンの公費接種は令和6年3月31日で終了しました。
定期予防接種
| 小児用肺炎球菌 | |
|---|---|
| 生後2ヶ月~7ヶ月未満 | 4週間隔で3回、生後12~15ヶ月で1回 |
| 生後7ヶ月~12ヶ月未満 | 4週間隔で2回、2回目から60日以上の間隔で1歳以降に1回 |
| 1歳~2歳未満 | 60日間以上の間隔で2回 |
| 2歳~5歳未満 | 1回 |
| B型肝炎 | |
|---|---|
| 生後2ヶ月から1歳未満 計3回 | 1回目から27日以上の間隔をおいて2回目を接種します。 1回目から139日以上の間隔をおいて3回目を接種します。 ※平成28年4月1日以降に生まれた方が対象です。 |
| ロタ(経口生ワクチン) | |
|---|---|
| ロタリックス | 生後6週から4週間隔で最終が24週0日(約5ヶ月半)。 合計2回 |
| ロタテック | 生後6週から4週間隔で最終が32週0日(約7ヶ月半)。 合計3回 |
※令和2年10月1日より ロタワクチンが定期接種になります。
対象者は令和2年8月1日以降に生まれた人です。
初回接種は14週6日までになります。
| 5種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風、不活化ポリオ、Hib) | |
|---|---|
| 1期3回 | 生後2ヶ月~90ヶ月未満(3~8週間隔) |
| 1期追加 | 初回接種終了後6月~13月までの間隔で1回 |
| BCG | |
|---|---|
| 0歳 | 標準的な接種時期は生後5ヶ月から8ヶ月 |
| ジフテリア、破傷風(DT) | |
|---|---|
| 11歳~13歳未満 | |
※日本では2歳以降の百日咳ワクチンの追加接種がないため、百日咳抗体の低下が問題となっています。
任意接種ですが、二種混合の代わりに三種混合ワクチンを使用することができます。
ご希望の方はお電話でお問い合わせください。
| 麻疹・風疹(MR) | |
|---|---|
| 1期 | 生後12~24ヶ月未満 |
| 2期 | 5歳~7歳未満で小学入学前1年間(年長時) |
| 水痘 | |
|---|---|
| 1歳~3歳未満 | 6ヶ月~1年の間隔で2回接種 |
| 日本脳炎 | |
|---|---|
| 1期初回2回 | 生後6~90ヶ月未満(3歳以後を推奨。 1~4週間隔) |
| 1期追加 | 初回接種後1年以上~90ヶ月未満 |
| 2期 | 9~13歳未満 |
| 子宮頸がん | |
|---|---|
| 小6~高1相当の女子 | 標準的な接種年齢は中学1年生 |
| シルガード9(9価) | 1回目の接種が15歳未満の方(計2回) 2回目は6か月あけて接種 1回目の接種が15歳以上の方(計3回) 2回目は2か月後 3回目は1回目から6か月後に(2回目から3か月以上あけて)接種 |
| ガーダシル | 2ヶ月間隔に2回、6ヶ月目に1回の計3回 |
※令和5年4月1日から、9価のHPVワクチンも公費(無料)で接種できるようになりました。
公費接種に関する詳細は川崎市のホームページ「川崎市:ヒトパピローマウイルス感染症(HPVワクチン)の予防接種について(city.kawasaki.jp)」、 厚生労働省のホームページ「9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について (mhlw.go.jp)」をご覧ください。
任意接種
| おたふくかぜ | |
|---|---|
| 1歳以上 | 4~5年の間隔をあけて2回の接種を推奨 |
| B型肝炎 | |
|---|---|
| 生後1ヶ月以上 | 1ヶ月間隔で2回、初回接種から6ヶ月後に1回の計3回 |
| A型肝炎 | |
|---|---|
| 1歳以上 | 1ヶ月間隔で2回、初回接種から6ヶ月後に1回の計3回 |
| インフルエンザ | |
|---|---|
| 生後6ヶ月~13歳未満※ | 2~4週間隔で2回 (※3歳以上で昨年2回接種された方は、1回でも可) |
| 13歳以上 | 1回 |
| 不活化ポリオ(IPV) | |
|---|---|
| 追加接種 | 5歳以上から7歳未満(任意接種)※ |
| 留学や海外渡航前の追加接種 | |
※ポリオに対する抗体下が減弱する就学前に追加接種を行うことを推奨します。
※当院では腸重積発症の紛れ込みを防ぐため、13週未満の初回接種をお勧めします。
(添付文書上は14週6日まで)
| DPT 三種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風) | |
|---|---|
| 5歳以上7歳未満 | 定期接種の四種混合4回目から6か月以上あける |
| 11~12歳 | |
※百日咳抗体価が低下することを受けて、就学前、11~12歳の二種混合の代わりに接種することを推奨します。
渡航前の予防接種(担当:院長、矢川)
渡航ワクチン(トラベルワクチン)
- 海外留学、海外旅行、海外転勤を計画されている方へトラベルワクチンの接種を行っています。
渡航先に応じて必要なワクチン接種を提案します。複数回の接種が必要なワクチンもありますので、渡航が決まりましたら、早めにご相談ください。家族での渡航の場合も対応いたします。 - 英文の予防接種証明書もお書きしておりますが、接種後1~2週間程度のお時間をいただいております。
- ワクチンによってはすぐに準備できす、取り寄せとなるものもございます。渡航が決まりましたら、早めにご相談ください。
※成人用3種混合ワクチン(Tdapと略す)は輸入国内未承認ワクチンです。
国内承認3種混合ワクチン(DPTやDTaPと略す)と比べてジフテリアの抗原量を減らしてあります。ご希望のワクチンをお伝えください。
予約制のためお問い合わせください。
接種証明書が必要な方は事前にお申し出ください。
成人の方の接種も行っております。
- A型肝炎
- B型肝炎
- 破傷風
- 日本脳炎
- 狂犬病
- 髄膜炎菌
- Tdap
- 腸チフス
こんにちは赤ちゃん外来
赤ちゃんが生まれて産院から戻ってくると、お母さんは赤ちゃんのちょっとしたことにも不安になるものです。
初めての予防接種や4カ月健診の機会にご質問・ご相談の時間を作りました。
あなたの「かかりつけ小児科医」はどんなささいなことでも相談にのります。
子育て中の女性医師がお答えします。
ゆったりした外来が特徴です。
是非、ご利用ください。
曜日・時間
火曜午前、水曜午前、金曜午前
担当医師の時間の調整がつけば、上記曜日時間以外も可能です。
受付でご相談ください。
利用目的
生まれて初の予防接種(生後2ヶ月~)
4ヶ月健診 赤ちゃん何でも相談(お乳の飲み方、湿疹、お臍がジクジクする、お臍が出ている、便秘、睡眠、離乳食など)
アレルギー相談 (※主な対象者は生後6ヶ月から7ヶ月頃までです)
担当医師
矢川 綾子医師(火曜午前、水曜午前、金曜隔週午前)
2児の母親、アレルギー専門医(日本アレルギー学会認定)、小児科専門医、「こどもの心」相談医(日本小児科医会認定)
予約方法
ホームページ・電話から「こんにちは赤ちゃん外来」の曜日・時間をご予約ください。
アレルギー外来
クリニック開設以来、アレルギー外来に注力してきました。アレルギー専門医(矢川医師) も診療に加わり、スタンダードな治療を基本としています。
アレルギーは、遺伝的要因と環境要因が複雑に絡み合って発症し、その病因や病態はさまざまです。
生活の質の向上や寛解・治癒を目指すために、アレルギー疾患の管理ガイドラインに基づいて、総合的に診療を行います。
お一人お一人にあった最適な治療を行うことを心掛けております。
アレルギー外来での診療内容
食物アレルギー、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、アレルギー性鼻炎、花粉症など
担当医師
院長、矢川医師(アレルギー専門医)
アレルギー外来の診療時間
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前(8:45~12:00) | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ |
| 午後(14:00~18:00) | ○ | ○ | ○ | - | ▲ | △ |
▲、△の予約枠はわずかです。
△は14:00~15:00までとなります。
※アレルギー外来は直接受付にご予約ください。
Web予約、自動電話では取れません。
- はじめての方は、受付 (044-852-7261) にお電話ください。
- 診察場所は2階小児科フロアと、3階健診フロアの場合があります。
予約の際にお確かめください。 - 食物アレルギー
食事は生活の基盤となるため、食事制限はお子様や保護者の方に多くの負担が強いられます。
近年の調査では食物アレルギーの有病率が増加傾向であり、社会的にも問題となっています。
当院では今までの症状の既往、食物の摂取状況など詳しく問診を行い、血液検査のデータとともに総合的に診断を行います。
また積極的に食物負荷試験を行うことにより「正しい診断に基づいた必要最低限の除去」を指導いたします。
食物負荷試験の結果から摂取可能量を判断し、食事療法を行います。
エピペンの処方(院長、矢川)
エピペンはアナフィラキシー症状に有効なアドレナリン筋注液の自己注射です。
エピペンは登録医のみが処方できます。
投与すべきタイミングや投与方法の指導を行います。
学校生活管理指導表、除去食申請書の記載を行うことが出来ます。
食物経口負荷試験(完全予約制)
本試験は、①病歴より原因と推察された食品が本当にアレルゲンであるかどうか、②未摂取の食品で、IgE抗体が陽性の食品に対する除去の必要性の有無、③原因食品をどの程度まで除去すればよいのか、④除去療法後にどの程度耐性を獲得したか(食べられるようになったか)を確認する検査です。
当院では開院以降、外来で安全に経口負荷試験(オープン法)を実施しております。
食物負荷試験は予約制です。
今までの既往や血液検査の結果から、安全を考えて、負荷する食品の摂取量を決定します。
負荷試験は強いアレルギー反応を引き起こすこともあるため、食品を少量ずつ分割摂取し、最終摂取から2時間程度経過観察を行います。
(8時半頃来院~帰宅の目安は13時~15時頃となります。) 負荷試験は時間をかけて症状を観察するため基本的に午前中に行います。
(月、火、金曜日のみ)
まずはアレルギー外来で相談していただき、必要に応じて食物負荷試験の予定を立てることになります。
※既往の症状や検査の結果によっては病院を紹介させていただくことがあります。
気管支喘息
気管支喘息の病態は慢性の気道炎症であるため、発作症状がない時でも喘息の重症度に応じて吸入ステロイドやロイコトリエン拮抗薬(長期管理薬)などで炎症を抑える治療を行う必要があります。
年少児では、客観的な評価が難しく、発作症状の頻度や重さで喘息のコントロール状態を評価しながらお薬の調節を行います。
小学生以上の年長児では客観的な指標として呼吸機能検査を行い、喘息のコントロール状態を評価します。
アレルギー性鼻炎
季節性のある花粉症やダニによる通年性のアレルギー性鼻炎は、くしゃみ、鼻汁、鼻閉などの症状により、生活の質の低下を引き起こします。
当院では血液検査やスキンプリックテストを行い、原因となるアレルゲンを確認することができます。
鼻炎症状に対して、抗アレルギー薬、点鼻薬等を用いた薬物療法を行います。
ダニアレルギーには環境整備指導を行います。
根本的な治療として舌下免疫療法を行うことも可能です。
舌下免疫療法(スギ、ダニ)
スギ花粉症やダニアレルギー性鼻炎の治療法のひとつに、アレルゲン免疫療法があります。
以前よりアレルゲンを含む治療薬を皮下に注射する「皮下免疫療法」が行われていますが、 近年では治療薬を舌の下に投与する「舌下免疫療法」が登場し、自宅で服用できるようになりました。
「舌下免疫療法」は、スギ花粉症またはダニアレルギー性鼻炎と確定診断された患者さんが治療を受けることができます。
対象は5歳以上のアレルギー性鼻炎の患者様です。
舌下免疫療法の治療期間は3年から5年間で、毎日舌下に錠剤を投与します。
アナフィラキシーなどの強いアレルギー反応は稀でありますが、初回投与時は院内で観察をさせて頂きます。
治療の相談を希望される方はアレルギー外来をご予約下さい。
アトピー性皮膚炎
乳児期早期より強い湿疹を繰り返す方は、体質的に皮膚のバリア機能が低下していることが近年明らかになっております。
また乳児期から湿疹がひどい状態が持続すると、経皮的に感作することによって食物アレルギーが発症することもあります。
当院では皮膚の炎症を抑え、良好な皮膚のバリア機能を保てるように、軟膏療法やスキンケア方法を指導いたします。
また食物アレルギーが合併することもあるため、必要に応じて検査を行います。
重症なアトピー性皮膚炎の方や、成人に移行する年齢の方は皮膚科専門医との連携も行っております。
専門外来(夜尿症、慢性便秘症、起立性調節障害、頭痛、小児心身症)
診察曜日と時間:月曜、火曜、水曜、金曜日の14:00~16:00です。予約制ではありません。ゆっくり時間をかけて診察いたします。
子どもの発達と心の外来
お子さんの発達や心の相談をお受けします。
ちょっとした心配が大きく膨らむまえに、またこんな相談はどこにしたらいいのかと。悩むときなどにお手伝いできたらと思っています。
例
- 成長発達や言葉の相談
- しつけの相談
- 集団生活での相談
- 保育園、幼稚園でのお友達同士の遊び方などの相談
- 学校でのお友達関係、学習の相談
- 思春期のお子さんへの対応の仕方の相談
公認心理士(臨床心理士)による発達知能、認知機能等の検査や心理相談を実施しながら支援しています。また、保育園・幼稚園、学校、地域療育センター、児童発達支援事業、専門医療機関等と連携しています。
※心理士の予約はWebでは取れません。医師の診察後に必要に応じて外来で予約していただきます。
キャンセルをする場合は必ずお電話にて早めにご連絡をください。ご協力お願いいたします。
(無断キャンセルの場合はキャンセル料として2000円が必要となります。)
*医師による診療
外来曜日:月・火・水・金曜日 診察時間:14:00~16:00(30分間隔)
ご利用方法:Web予約システム
子どもの発達と心の外来は、一般診察の枠では予約できません。「子どもの発達と心の外来」の予約枠をご利用ください。
初めて「子どもの発達と心の外来」の受診を希望される方は、来院前に受診のご案内にある「初診用問診表」を記入の上、ご来院ください。
予約時間を過ぎた場合は、診察を受けることが出来なくなることもございます。必ずご予約の時間にご来院ください。
*心理士のカウンセリング
曜日
火曜日 午前9:00から12:00まで(完全予約制)
担当
臨床心理士・公認心理士の資格のあるベテラン心理士
内容
発達相談・発達検査(検査は保険にて対応)
心身症・不登校など「心の問題」のカウンセリング
初診の方は、まず、鈴鹿院長・矢川医師の子どもの発達と心の外来を予約してください。